枕が濡れていた。胸が締め付けられるように苦しいのに、どこか心は清々しかった。
今度はいつ会える? そんなことすら約束しないで。
私は彼女に対して結構無責任なことを言ったもんだ。たしか彼女の家は茶道をやっているとか言っていた。当時の私はそれを習字やそろばんといった習い事程度に考えていたけど、彼女にしてみれば、それはつまり、家業を継ぐこと、その町でずっと暮らしていくことを意味していたのかも知れない。実際そういうものなのかは知らないけれど、彼女はどこか覚悟していたように思う。
あの頃の私は、毎日が特別で。だからこのことも、大して気にとめてなかったんだろう。
それにしても彼女のことをすっかり忘れてたんなんて。いや、忘れたのではなく、思い出さないようにしていたのかもしれない。私は、私の世界を広く広くすることにとらわれていたのだろうか。
体を起して、窓を見る。眩しい光は斜めに差し込んでいる。時間はやはり午後三時。
「行こう」
目的の場所が見つかった。やるべきことが見つかった。
バッグを取り、靴を履く。
そしてその前に、会わなければならない人がいた。
* * *
「……行くの?」
海沿いの道、涼しげな風の中、少女は堤防に腰掛けていた。まるで私を待構えていたかのように。いや、きっとそうなんだろう。どうして私がここを通るのを知っていたのか、そういうことはもう疑問に思わなかった。
「うん。私、行かなくちゃ」
「どうして」
「ここは、私のいるべき場所じゃないんだ」
「ここは、お姉さんの望んだ場所じゃなかったの?」
海を眺めて、私は言う。
「うん……確かに私は、ここへ逃げて来た。変わることの恐怖から。変わりたくないから、だから時間が止まったんだ」
「だったら」
「でも、だめなんだよ、それじゃ」
私は首を振る。
「どうして?」
「それじゃだめなんだ。それじゃ先に進めないの」
私は、少女と、静かに話す――
なっちゃん、都会ってね、いろんなことがあって、毎日忙しくて。なんていうかな、みんな急いでるんだ。立ち止まる暇もなく。私もそうだった。
自分で前を見て歩いていたはずなのに、気が付いてたら、何かに背中を押されるように、流されるように進んでる。それでいつの間にか、進むべき道が分からなくなっちゃっていたの。
私は今どこにいるんだろう、どこに進めばいいんだろう。
私って、何なんだろう。
そう思ったとき、私は足が止まって、もう進めなくなってしまった。その先は見えなくて、不安で、怖くて。
だから、未来から逃げるように、この町――過去の止まった時間の町に来たんだ。
振り返るのは、別に悪いことじゃないし、逃げたっていいと思う。でも、そこで止まって、動かなくなっちゃうのはきっとよくないんだ。
変わることを恐れちゃいけない。変わるってことが、未来へ進むことなんだ。雲が流れて、潮が引き満ちて明日が来て。秋になって、冬が始まって。春が過ぎて、そしてまた来年の夏が来る。
人も、同じなんだ。変わっていくから、生きてるんだ。
「そっか……」
「……なっちゃん、やっぱり、大人になるの、怖い?」
「どうかなあ。お姉さんは、大人になってよかったって思ってる?」
「うん……そうだね」
あの言葉を思い出す。かつての自分に、私は大切なことを教えられた。
「大人になるってことは、自分の世界が大きくなるってこと。確かに大人になれば、いろいろ縛られちゃったりするかもしれない。でも逆に、出来ることもいっぱい増える。自分が本当に進みたい道を歩いていけるんだよ」
「お姉さんは、その道、みつかった?」
「あはは、まだ迷ってるけどね。それでここに来ちゃった。きっとこれからも迷って、また来ちゃうかもしれない」
私は少女の手をとる。
「でも大丈夫。地に足がついて、前を見て歩いていける。迷って、戻って、また進んで。その繰り返しで、生きていくんだ」
その小さな体を、抱きしめた。
「この町に来てよかった。そして、なっちゃんに会えて本当によかった」
「うん……あたしも、お姉さんに会えて、よかったって思うよ」
* * *
手をつなぎ、二人歩いてく。照りつける夏の日差しは、アスファルトをまぶしく照らしていた。そして、あの場所へたどり着く。
「あたし、ここから先には行けないの」
「うん……」
その前で二人は立ち止まる。
あの頃は無かった、この町には無いはずの黄金の向日葵畑。過去と現在との、境界線。
「ここで、お別れだね」
少女は、小さくこくりと頷いた。その横顔に、私は静かに言葉を伝える。
「これで、やっと前に進めると思う」
「うん」
「ありがとう。なっちゃん」
繋いだ手が、すっと離れて、
――さようなら
その存在が、薄くなっていくのを背中に感じながら、
――さようなら
私はその輝く光の中へと入っていく。
* * *
背丈ほど伸びた、太い茎。その上に咲く金の花びら。それらを手でよけ、進んでいく。
時を越える、現在(いま)へと続く向日葵のトンネル。その向こう、茎と葉の隙間から漏れる光の出口には、一人の人影。
私は近づき、そして彼女はゆっくりと振り向いた。
「ああ、やっぱり」
麦わら帽子の下の表情が、にっこりと笑いかける。
「ナツだったのね。さっき、ちらっと見かけたの」
「なっちゃん……」
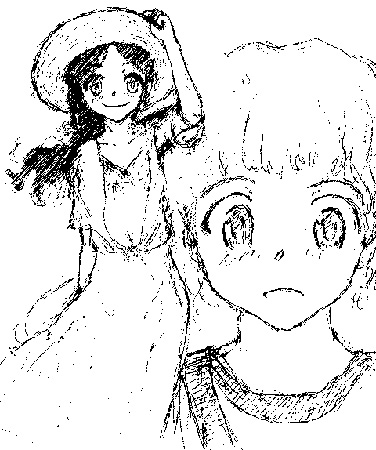
軍手に小さな鎌を持ったその姿は、随分と落ち着きはらった柔らかい女性といった感じだ。その長いスカートは農作業にはどうかと思うけど。
「ショート似合うねえ。今日こっちに来たの?」
「うん。故郷に一人旅ってね」
「一人? あれ、でも気のせいかな、さっき、小さな子が一緒にいたような気がしたんだけど」
「ああ、あの子……ちょっとね」
過去の存在であるはずの幼いなっちゃん。今のなっちゃんにも、なんとなく見えてはいたのだろうか。
「ふふ〜ん、ひょっとして、ナツの子供?」
「へっ?」
何を言ってるんだ、この子は。相変わらずいたずら好きというか。
「私はまだ結婚だってしてないって」
それにあんな年の子供、私の年齢からは少々無理がある。
「うふふ、そうよね。でも、そっくりだったなあ」
「うん、昔のなっちゃんにね」
「やだ、違うわよ」
「え?」
「似てたのはあんたの方よ。小学校のときのあんたにそっくり」
その言葉で、私は一気に記憶が駆け巡る。
――そうか。
――そうだ。
そうだ、忘れていた。三年生になったときのクラス替えで、私達は出会ったのだ。
かつて私は自分の名前が嫌いで、友人にあだ名で呼んでもらっていた。だけどその呼び名がお互い被ってしまい、結果私はナツと彼女に呼ばれるようになったんだっけ。
彼女の名は、柊棗(ひいらぎ なつめ)。
そして私は、七津花子(ななつ はなこ)。
それまでのあだ名は、苗字から取って、なっちゃん。
「……そうだったの」
どこかで会ったような気がしたのに、思い出せなかったのはそういう理由だったのだ。
私は――
この町で――
かつての私と出会ったのだ――
だったら、そうだったのなら。私はもっとたくさん伝えたいことがあったんじゃないだろうか。そんな思いに駆られながら、でもやっぱり、何も言えなかったのだと思い当たった。私は自分で言ったじゃないか。私はここにいるべき存在ではない、と。
まるで過去の自分と決別したかのような気分だったけど、今目の前にいるなっちゃんは、私の中に確かにあの子を見たのだ。きっと、今私が立っているこの場所は、ゴールでもスタートでも、ましてやリセットでもない。前にも後にもなだらかに続く道の途中。ごく自然なことなのだ。
「ちょっと、ナツどうしたの?」
知らず、私の目から涙がこぼれていたらしい。あわててそれを拭う。
「大丈夫。ちょっと懐かしくて、うるっと来ただけ」
「なに、そんなに私に会いたかったの〜?」
にやにやして、上目遣いで私の顔を覗き込んでくる。やっぱりなっちゃんは全然変わってない。
「違っ、そうじゃない……けど、いや、そうなのかな」
「えっ」
妙に顔を赤らめるなっちゃん。
「そ、それにしても、あの種で、こんなになったなんてねえ」
照れ隠しに私は話題を変える。
「……いやいや、そんな簡単にはならないわよ。私がずっと手入れしてきたの」
天に向かう茎に触れ、我が子のようにその大輪を見つめる。
「もう趣味みたいなものね。本当は駅の土地らしいけど、好きにしていいって」
私達の秘密の計画は、ちゃんと実を結んだのだ。それが未来への勇気を抱かせて。
「――なっちゃん、今日の夏祭り、一緒にいこうよっ」
あの夏、果たせなかった約束を、今。
「もちろん。ひょっとしてあんた、それ目当てで来たの?」
私はその手をとって。
「たまたまだよっ!」
歩いていく。
ナツとなっちゃんの夏 完